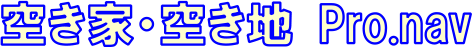空き家の解体:手順や費用についてのポイントを説明します。
空き家の解体は、単に建物を壊すだけでなく、多くの手続きと費用、そして、近隣への配慮が必要になってきます。
計画的に進めるために、全体の流れと重要なポイントを把握しましょう。
1. 解体前の準備(重要な手続きと業者選定)
解体工事を始める前に、施主(所有者)が行うべき準備と手続きが最も重要です。
▢ 残置物と所有権の確認
- 残置物の処分・整理
家の中にある家具や家電、衣類などの残置物は、原則として解体工事費用に含まれません。
事前に自分で処分することで、処分費用を削減でき、解体費用の節約につながります。 - 所有権の確認
登記簿上の所有者が亡くなっている場合など、建物解体や残置物処理を行うために、現在の所有者(権限のある方)を確認する必要があります。
▢ 解体業者の選定と契約
解体工事の成否は業者選びにかかっています。
最低でも2~3社から相見積もりを取り、比較・検討が必要です。
- 許認可・保険: 「建設業許可」または「解体工事業登録」があるか。
万が一の事故に備えて損害賠償保険に加入しているか。 - 見積書の内訳: 単価(坪単価など)だけでなく、「仮設工事費」「廃棄物処理費」「整地費用」など、項目が細かく明確に記載されているか。
不当な追加請求がないかを確認します。 - 近隣への配慮: 工事前の挨拶回り(施主と業者が一緒に行くのが理想)や工事中の防音・防塵対策に丁寧に対応してくれるか。
- マニフェスト(産業廃棄物管理票): 廃棄物が適正に処理されたことを証明するマニフェストの
写しを工事完了後に発行してくれるか。
▢ ライフラインの停止と届出
- ライフライン停止: 電気、ガスは使用停止と撤去を手配します。
水道は工事中の散水などに使うため必要なので、解体終了まで残すのが一般的です。 - 各種届出: 建設リサイクル法に基づく届出(床面積80m²以上の場合)や道路使用許可の申請が必要になります。
これらはほとんどのケースで解体業者が代行します。 - アスベスト調査: 2022年4月以降、建物の規模にかかわらず解体工事前にアスベスト含有調査が義務付けられています。
この調査と届出も業者に依頼します。
2. 解体工事と費用相場
費用相場(坪単価の目安)
費用は、建物の構造や、立地などによって大きな差が出てきます。
| 構造 | 坪単価の目安 |
| 木造 | 3万円~6万円/坪 |
| 軽量鉄骨造 | 4万円~7万円/坪 |
| RC造(鉄筋コンクリート造) | 6万円~9万円/坪 |
※上記以外に、残置物処分費、付帯物(塀、庭木など)の撤去費、地中埋設物(浄化槽、古い基礎など)撤去費、アスベスト除去費などが加算されます。
補助金・助成金の活用
老朽危険家屋の解体を促進するため、多くの地方自治体が補助金・助成金制度を設けています。
- 支給額は、解体費用の1/5~1/2程度、上限50万~100万円が多いです。
- 「特定空き家」に指定されている、倒壊の危険があるなど、支給には厳しい条件があります。
- 必ず工事着工前に自治体窓口に相談・申請が必要です。
3. 解体後の手続き(建物滅失登記)
解体工事が完了したら、建物滅失登記を申請し、法的に建物を消滅させる必要があります。
- 建物滅失登記の申請: 建物がなくなったことを登記簿に反映させる手続きです。
解体後1ヶ月以内に、所有者(相続人)などが法務局に申請する義務があります。 - 目的: この登記を行うことで、翌年度以降の固定資産税の課税を停止できます。
登記を怠ると、存在しない建物に税金がかかり続ける可能性があります。
ただし、所有する土地は更地になるため、土地の固定資産税が上がります。
不動産取引には、解体がつきものです。
ご不明な点など、ご相談やご依頼は、当社までお気軽にお尋ねください。